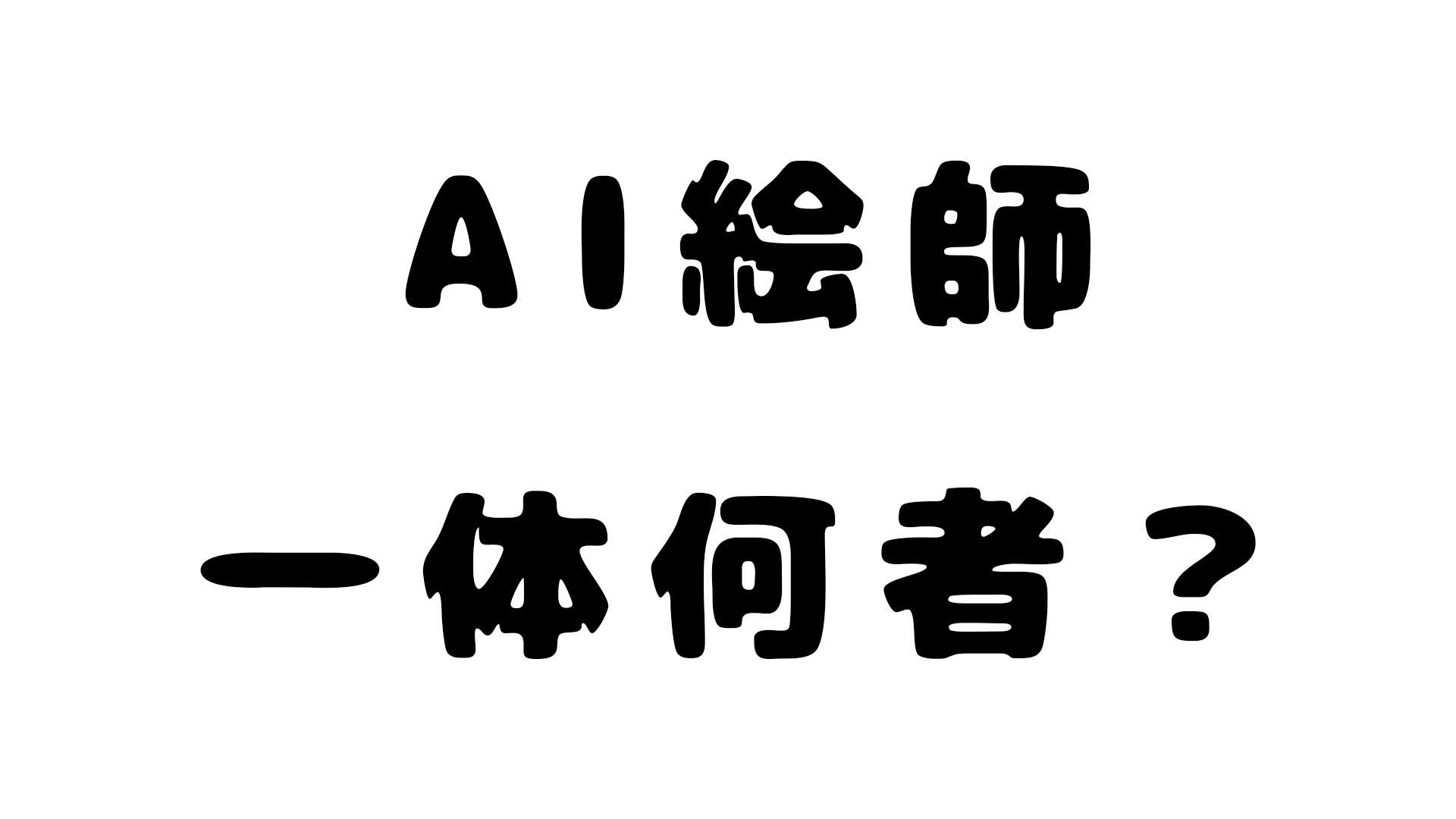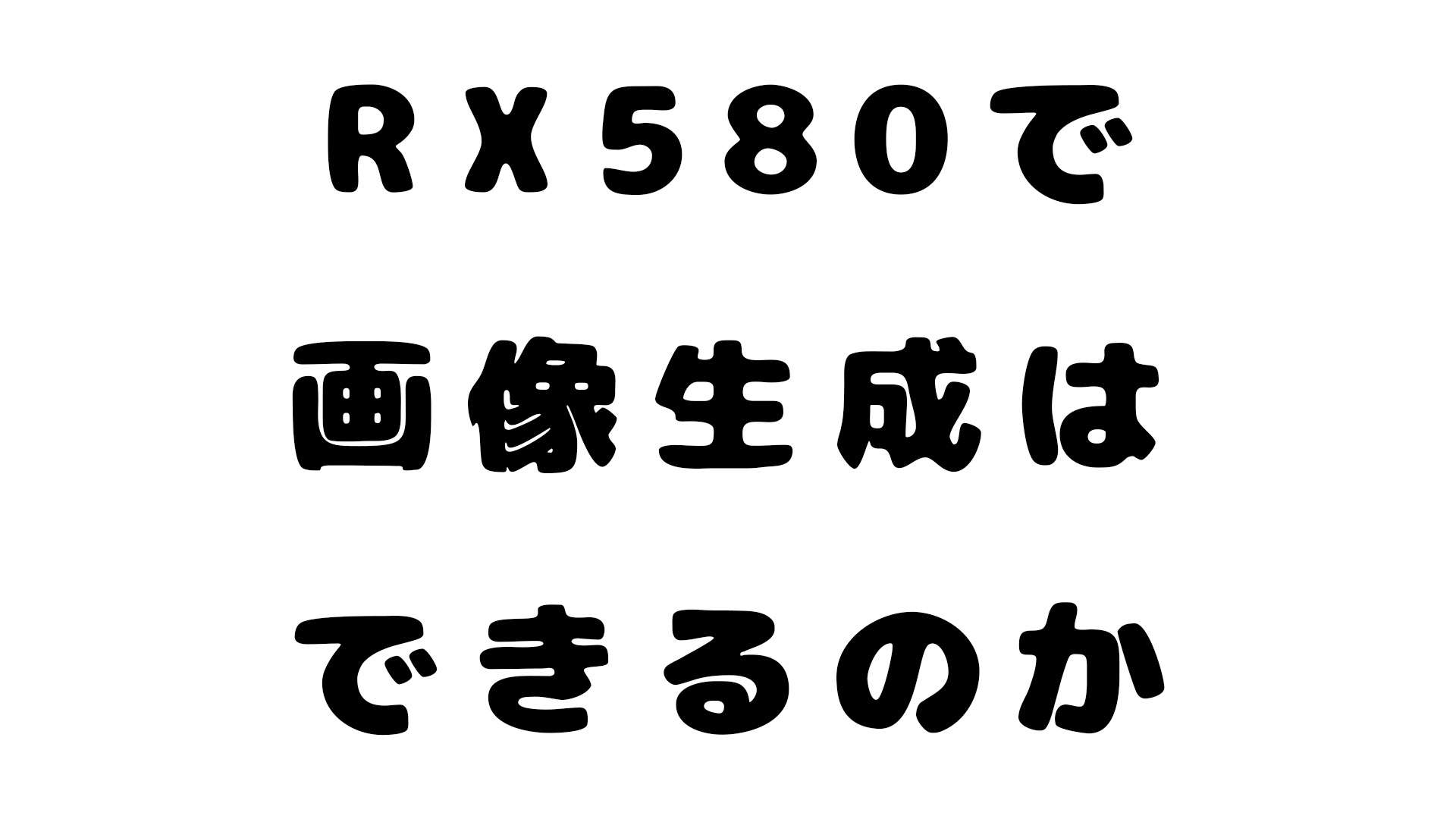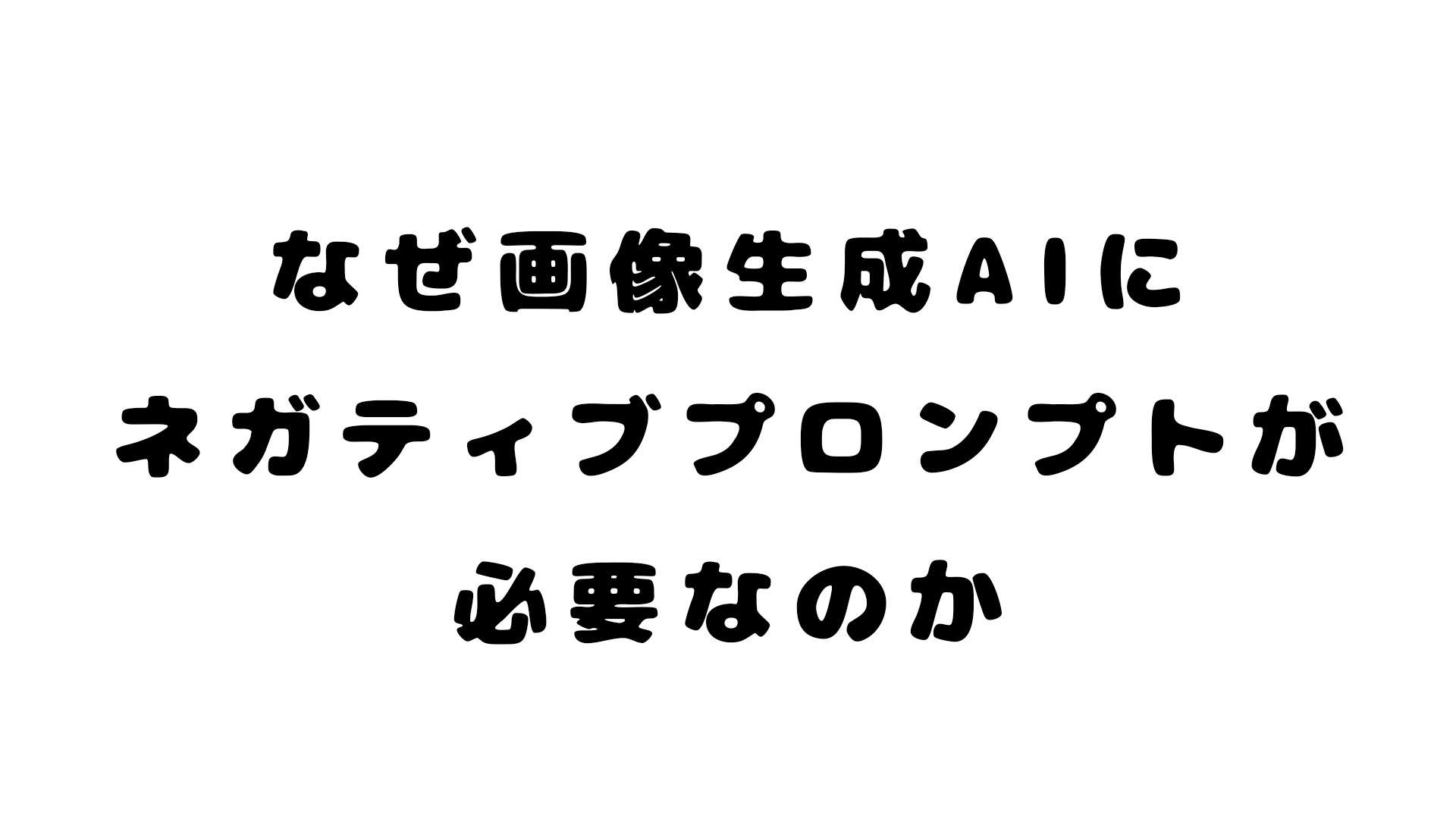先日、生成AIによるイラストの出力をしてみたのですが、世の中にはこれをより高い技術で行い「AI絵師」と呼ばれている人たちが存在しています。AIによるイラスト出力は、学習に使用されたデータによる問題、AIイラスト自体の著作権の問題、またAIでイラストを出力する人を「絵師」と呼んでいいのか、など様々な問題があるようです。
実際にAIでイラストを出力してみた経験から、その一連の過程を考え、AI絵師とはどのような立ち位置なのか、少し考えてみたいと思います。
AIイラストを出力するだけ?
昨今、SNSやポートフォリオサイトで「AI絵師」を名乗るアカウントを多く見かけるようになりましたが、「AIに画像を生成させただけで絵師を名乗るのか?」という疑問の声も少なくありません。それはプロンプトを入力から、イラストが出力される一連の流れに、イラストレーターとしての技術は必要とされず、生成結果を含めたすべての絵に自身は存在しないからです。
特に、機械学習に使用されているデータは他人が描いたものであり、出力される結果もその学習データから導き出されたものです。つまり、生成AIによって出力される絵そのものは他人の絵ということになります。
想定通りに出力するには技術がいる
一方で、生成AIで自身が思い描いたものを出力するには、相応の技術と試行錯誤が求められます。
プロンプト設計に始まり、モデルの選定、シード値や解像度、構図や色味への微調整、さらに「出力ガチャ」に付き合う忍耐力と、それを乗り越えるアルゴリズム的な工夫も必要不可欠です。このように、想定した結果となるようPCに指示を出す行為は、絵師というよりも、プログラマーに近いと言えるかもしれません。
欲しいイラストをピンポイントで引き出す作業は、テキストという曖昧な命令文を成果物へと変換する「生成指示スキル」で、その本質は、システムエンジニアやインターフェース設計者に近いかもしれません。
手修正を加えたら絵師?
また、生成されたイラストにPhotoshopや他の画像編集ツールで手を加える人もいるようです。特に、生成AIは、通常の人間であれば、描くことのない不自然な絵を描くことがあるので、手足や指に修正を入れたり、服の細部を整えたり、背景に小物を足したりする必要が出てきます。
AI絵師の中には、そういった小規模な修正にとどまらず、線画で出した生成AIイラストに自身で色を塗ったり、生成イラストを自身で描き直したりするなどして、より大規模な修正を加えることで自身の成果物とする人もいるようです。
画像編集者が近いかも
手修正と言っても内容は様々ですが、これら多くの修正作業は、果たして「絵師」の仕事と言えるのでしょうか。個人的には、「画像編集者」や「イメージエディター」と呼ぶ方がしっくりくる気がします。
もちろん、手を動かすことには意味がありますし、様々な過程を通して成果物を公開するまでの一連の作業を否定するものでもありません。ただ、「自らゼロから描く」という点においては、伝統的な意味での「絵師」とは少しズレがある気がします。
呼び方を変えてみるのは?
そもそも、これらの行為を「絵師」と呼ぶからこそ、無用な対立や誤解が生まれるのではないでしょうか。であれば、いっそ呼び方をアップデートしてみるのもひとつの手だと思います。
たとえば、「生成エンジニア(Generation Engineer)」や「プロンプトエンジニア(Prompt Engineer)」などの呼び方が挙げられるでしょう。これは、AIによる出力を意図通りに導くスキルを持つ人に相応しい名称であり、画像生成モデルと対話しながらアウトプットを最適化する技術者、まさにエンジニアです。
もしくは、プロンプトの設計者として「プロンプトデザイナー(Prompt Designer)」、画像編集者として「AIイメージエディター(AI Image Editor)」といった呼び方もいいかもしれません。
もちろん、これらのスキルは、画像生成AIだけでなく、その他の生成AIスキルとしても有用であり、各分野での知識を習得できれば、今後、AI絵師のみならず、多方面のフィールドで活躍が期待される能力だと考えられます。
自身の活躍の場をAI絵師に限定することなく、自身が持つ言語化能力の高さや設計能力の高さを肩書に、希少性の高い人材として、積極的にアピールしていくのもいいのではないでしょうか。